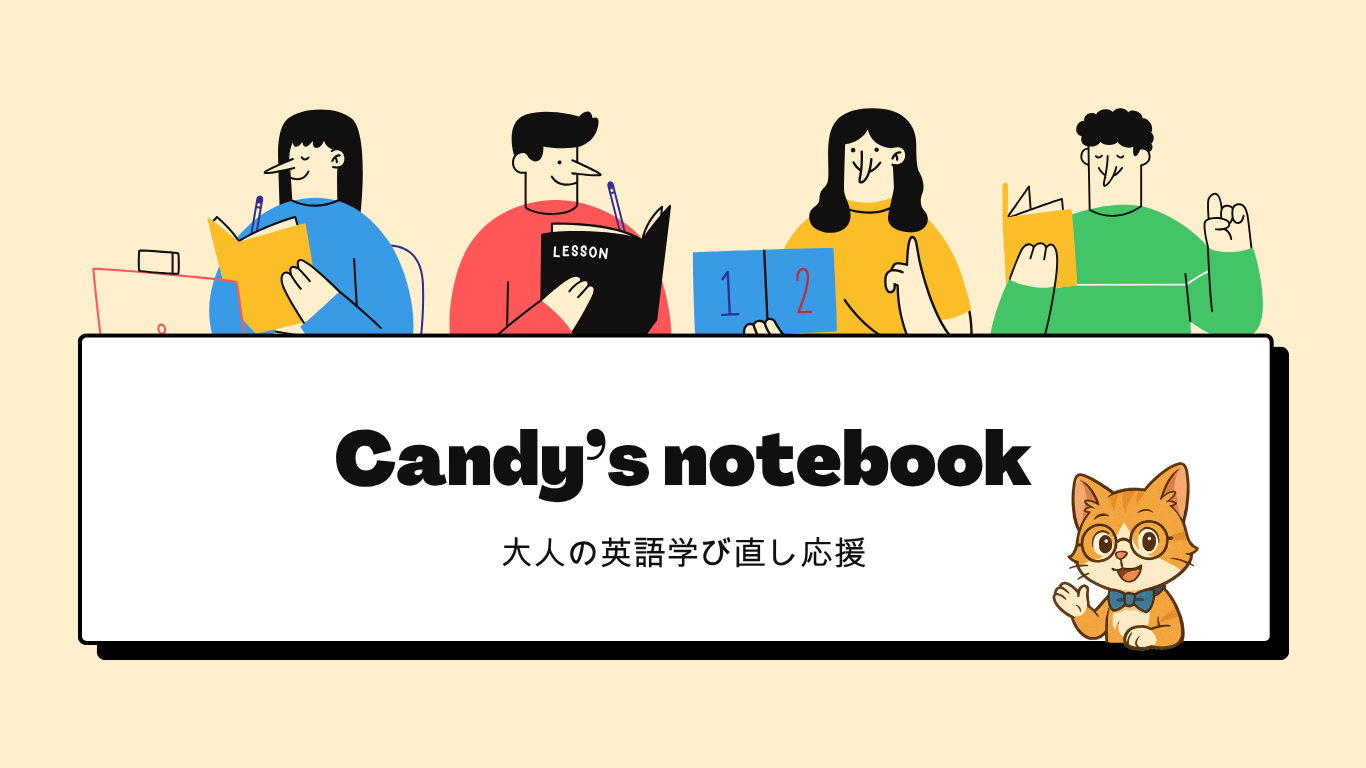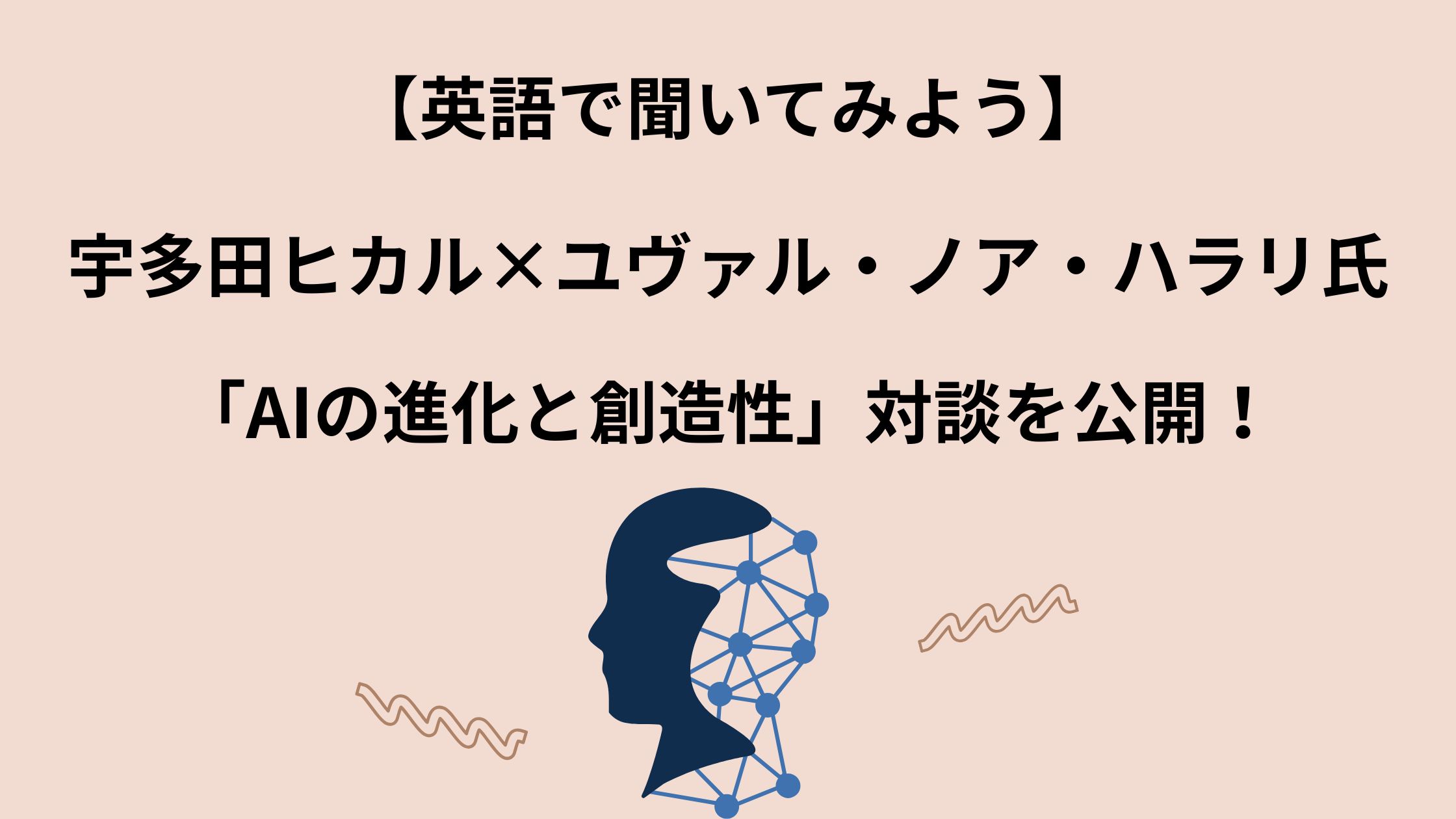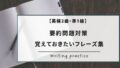歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリ氏と宇多田ヒカルさんによる対談「AIの進化と創造性」を公開!
ソーシャル経済メディア「NewsPicks」YouTubeチャンネルにて公開中

びっくりなコラボだったね!興味深い話がたくさんだったよ〜!
宇多田さんのファンとして、曲作りへの取り組み方や人が努力して作り出すものについての話も心に響きました。
日本語字幕付きで聞き取りやすい英語も多かったので、英語学習の間に聞いてみて♪
内容を少しまとめてみました!
対談の背景
- 対談は7月13日、ロンドンのフロイト博物館で行われ、NewsPicksおよびYouTubeチャンネルで公開中
- テーマは「AI時代における創造性とは何か?」「音楽とテクノロジーの共存」「情報過多の時代における人間らしさ」
ユヴァル・ノア・ハラリ氏について
イスラエル・エルサレムのヘブライ大学で教鞭を執る歴史学者。
著書『サピエンス全史』『ホモ・デウス』『21 Lessons』は世界中で翻訳され、AI・政治・哲学・宗教といった幅広いテーマで人類の行く末を問いかけています。
ハラリ氏の視点:「AIは極めて創造的になりうる」
- AIは囲碁のAlphaGoのように、人間を超えるパターンを発見し、人間が思いつかない美的・感情的体験を生み出す可能性があると指摘
- AIは数十億単位のデータを処理し、リアルタイムでカスタマイズされた音楽や映像を生成できる能力を持つ。
宇多田ヒカルさんの視点:「人間らしさ=プロセスにある価値」
- 宇多田さんは、音楽制作において「偶然性」「アクシデント」「努力の跡」が作品の魂になると語る
- 人が共感するのは「感情を込めた物語」を含む過程であり、完璧なAI生成物よりも人間の刹那的な演奏や失敗に心動かされると強調。
AIと人間、共創の未来へ
- ハラリ氏と宇多田さんは、AI進化に「恐れ」ではなく「好奇心」を持つことの重要性で一致
- AIの創造力と、そこに込められた人間の背景や意図をどう織り交ぜていくかが、これからの創作の鍵になるという視点が提示された。
クリエイターにとってのヒント💡
- 完成品のクオリティよりも、「制作の過程」そのものが共感と価値を生む時代。
- クリエイターは作る過程を記録・共有することでファンとのつながりを強められる。
- 日常の小さな発見や取り組みを発信するスタイルが、デジタル時代における新しい表現方法
🔎 まとめ
- AIは「創造する存在」になり得るが、それだけでは心を動かせない。
- 人間の「物語性」「偶然性」「努力の過程」こそが創作の本質。
- AIと共に歩むこれから、自分自身を探求する好奇心こそが最大の武器
🎧 対談動画をぜひフルで視聴して、クリエイティブな問いを耕してみて!
ふだん聞けないクリエイターと哲学者の対話から、新たな視点が得られます!
✨️対談に感動!(by Yuki✏️)
大好きな宇多田ヒカルさんと、ユヴァル・ノア・ハラリ氏の対談が実現するなんて、本当にびっくりでした!
宇多田さんの音楽は、私にとって唯一無二の存在です。どきどき・わくわくするイントロに始まり、メロディが重なっていく展開、そしてアレンジの妙…。1曲の中にまるで物語があるようで、聴き終わる頃には1冊の小説を読み終えたような余韻。
歌詞のひとことひとことが心に刺さる。感情の機微や日常の小さな揺らぎを、こんなにも美しく、深く描けるなんて…と、心が揺さぶられます。
対談の中で語っていた宇多田さんの曲作りで悩んでいるときの比喩「ボートの上で魚をまっているような感じ」が心に残りました。
ファンとしても、そしてこのサイトを運営しているクリエイターとしてとても興味深く拝見しました。
自分は何かを作りたい気持ちがあっても、人々は感謝してくれるのか。
自己満足?…私は人々と共感していきたい。